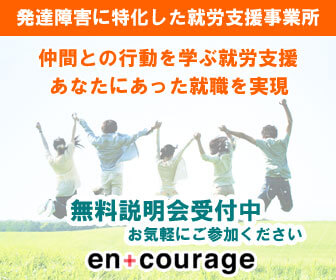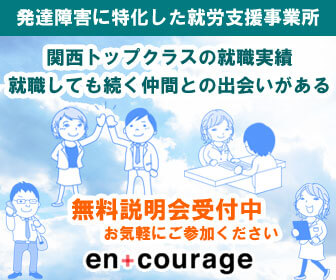自分らしく働くために!発達障害を上手く開示するコツ3選
発達障害の当事者かつ支援者です
エンカレッジ大阪のスタッフNと申します。
53歳男性で、私自身も発達障害(ADHD)の診断を受けています。また、25歳の時にADHDの多動が災いして交通事故に遭い、高次脳機能障害も負っています。記憶力、衝動性、注意力等のコントロール不調から、事務処理における苦手がたくさんあります。
でも、他のスタッフに理解と配慮を頂きながら、ADHDの障害特性である「しゃべり過ぎ」を逆手に取った講師力で、障害当事者の経験を交えた講座をご提供しています。
今日はそれら講座の中から、「発達障害を開示するうえでのコツ」について、概要をお話しします。
発達障害があることを隠しながら暮らしていくのではなく、気持ちスッキリ、堂々と開示できる。そして、障害を理解してくれる人たちから配慮を受けながら、自分にできることで周囲に貢献し、安定した生活を送って頂けるよう願っています。
(なお、障害を開示するのはあくまで個人の自由です。開示は強制されるものであってはなりません。)

障害開示のコツ3選
【1】障害開示の3ステップ
障害を開示する際には、いきなり「私、発達障害なんです!」と切り出すよりも、段階を踏んで伝えることが大切です。
1)「“発達障害”ってご存じですか?」から始める。
開示の第一歩は、相手が発達障害についてどのくらいの知識を持っているかを探ることです。
「発達障害ってご存じですか?」という質問から始めることで、相手が「よく知らない」と答えれば、簡単な説明から入ることができます。もし「知っている」と答えた場合でも、相手の認識が正確かどうかを確認しながら話を進められます。このステップを踏むことで、相手は「どんな話が始まるのだろう?」と心の準備ができ、あなたの話を真剣に聞く姿勢になってくれます。
2)「私、実は発達障害なんです」と伝え、「最大の困りごと」を(まず、ひとつだけ)伝える。
相手の理解度を確認したら、いよいよカミングアウトです。しかし、一度に多くの情報を伝えすぎると相手は混乱してしまいます。まずは、「私、実は発達障害なんです」 とシンプルに伝え、「記憶するのが苦手で、同じことを何度も聞いてしまうことがあります」 といったように、最も困っていることをひとつだけ伝えましょう。
こうすることで、相手はあなたの障害を理解するきっかけを得ると同時に、「〇〇さんには配慮が必要なんだな」と具体的にイメージしやすくなります。
3)詳しく伝える
相手があなたの話を真剣に聞いてくれていると感じたら、3つのポイントを意識しながら、さらに詳しく伝えていきましょう。
■苦手なこと
「私はこういうことが苦手です」と具体的に伝えます。例えば、「会議中の長時間の集中が苦手で、途中で話が頭に入ってこなくなってしまうことがあります」といった具合です。具体的なエピソードを交えながら話すことで、相手はより深く理解できます。
■適応のために努力していること
ただ苦手なことを伝えるだけでは、「弱音を吐いてばかりの人だ」という印象を与えかねません。そこで重要なのが、「苦手なことを克服するために、自分なりにこんな努力をしています」と伝えることです。
「会議の内容を理解できるよう、常にメモを取りながら参加しています」など、具体的な努力を伝えることで、「この人は、自分の課題に向き合って努力しているんだな」という前向きな姿勢を伝えることができます。
■助けてもらえるとありがたいこと
最後に、相手に「では、具体的にどうしてあげたら良いのだろう?」と思ってもらったところで、「こうしてもらえると助かります」と具体的な配慮をお願いします。
「会議後に、私に覚え間違いがないか確認させて頂けるとありがたいです」など、相手に負担を掛け過ぎない形でお願いすることが大切です。
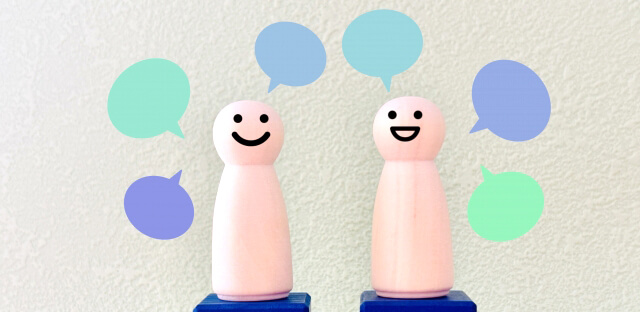
【2】障害開示で避けるべき3つのNG行動
せっかく開示しても、以下の行動をすると反感を買いやすいので気をつけましょう。
◎診断名しか言わない
例えば「私、自閉症なんです」とだけ伝えても、相手は「自閉症ってどんな障害なんだろう?」と思うだけで、どう対応していいかわからなくなってしまいます。診断名だけでなく、具体的な困りごとや必要な配慮をセットで伝えることが重要です。
◎諦めや恨み言を口にする
「どうせ私なんて、何度言われても仕事を覚えられないんです」や「上司に何度言っても理解してもらえないんですよ」といった諦めや恨み言は、相手にネガティブな印象を与えてしまいます。相手は「この人はどうせ頑張らないだろう」「話を聞いても無駄かな」と感じてしまい、協力したいという気持ちを失ってしまうかもしれません。
◎「発達障害だから仕方ない」と努力から逃げる
障害は、自分の努力だけではどうにもならない部分もあります。しかし、「発達障害だから仕方ない」と開き直って、できる限りの努力を怠ってしまうと、相手はあなたに対して不信感を抱くようになります。「できることは自分でやる」という姿勢を見せることで、相手は「この人なら協力してあげたい」と思ってくれるはずです。
【3】開示した後の振る舞い方
障害を開示したからといって、それだけですべてが上手くいくわけではありません。開示後も、周囲との良好な関係を築くための努力が必要です。
◎失敗したら、まずは素直に謝罪
発達障害の影響でミスをしてしまった場合でも、まずは「ごめんなさい」と素直に謝罪することが大切です。(「発達障害だからミスしても仕方ないんです」という“言い訳”を最初に言ってしまっては、信頼を得ることはできません。)その後に、「私の不注意で、〇〇の作業が漏れてしまいました。今後はチェックリストを作って再発防止に努めます」といったように、障害の影響と再発防止策を説明しましょう。
◎得意なことについては誇りを持ち、責任を持って取り組む
発達障害者だからといって苦手なことばかりではなく、できること、得意なこともあります。例えば、ADHDの特性である「衝動性」は、失敗を恐れず困難に立ち向かう原動力になることもあります。自分の得意なことについては誇りを持ち、責任を持って積極的に取り組むことで、周囲からの信頼を得ることができます。
◎非障害者でも有り得る「暮らしづらさ」を理解し、自分にできるサポートをする
発達障害を持つ人だけでなく、非障害者にも「人前で話すのが苦手」だったり、「子育て」や「家族の介護」といった家庭の事情等、「暮らしづらさ」を抱えている人はたくさんいます。
自分ばかりが配慮を求めるのではなく、周囲の人の困りごとにも目を向け、「何か手伝えることはありますか?」と声をかけるなど、自分にできるサポートをすることで、豊かな信頼関係を築くことができます。
より生きやすく、働きやすく
障害を適切に開示できれば、周囲の理解と協力を得ることができ、より生きやすく、働きやすい環境を自分で作っていくことができます。
もし、発達障害を開示しながら働くことをお考えであれば、ぜひこの記事でご紹介したコツを意識しながら取り組んでみてください。
そして、もし一人で就職・就労を目指すことに不安を感じているのであれば、私たちエンカレッジにご相談ください。あなたの就労を全力でサポートさせて頂きます。

発達障害に特化したエンカレッジ

発達障害のある人に特化したエンカレッジは、あなたの「働きたい!」をサポートします。
就労移行支援事業所は、大阪(本町、心斎橋、天満橋)・京都(京都駅、京都三条)・東京(早稲田駅前)・神奈川(横浜関内)の7拠点、自立訓練事業所は、encourage doors(北浜)で説明会の申込み・相談を受け付けておりますので、お気軽にご参加ください。