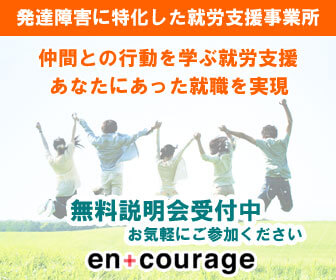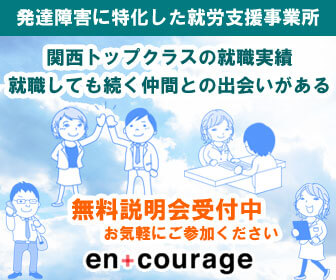寄り添うとは、背を向けないこと――発達障害の家族を支えながら考える支援のかたち
みなさん初めまして、京都のIです。
エンカレッジで就労移行支援のお仕事を始めて早3か月になります。
前職では居宅介護サービスの生活支援員の仕事をしておりました。
その中で支援があってこそ日常が保たれるという事実を知ることができた一方で、どれだけ“できる”ようになっても、その裏で「波」があるということも見えてきました。
気分に波がある日、何でもこなせる日、逆に全く動けない日もあります。
そんな時、私は「できない日=失敗」ではなく、「次の支えを考える時間」「環境を見直す機会」と捉えるようになりました。
そして気づいたのは、“寄り添う”という言葉には優しさだけでは足りない重みがあるということです。
この記事では、家族を支える視点から
「日々の波をどう捉えるか」
「本当に寄り添う支援とは何か」
「未来に向けてともに歩む姿勢」
について、私の体験を通してお話ししたいと思います。
寄り添う~家族を支える視点から~

私の妻は発達障害と鬱病があり、障害特性から日によってできることに波があります。
苦手な料理ができる日もあれば、得意な洗濯ができずどうしても動けない日もある。
そんな日は「ごめんね」と謝る妻に、「謝らなくていいよ」と伝えながらも、私の胸の中にはいつも小さな無力感が残っていました。
全部を支えてあげられたらいいけれど、私にも仕事があります。
ヘルパーさんも訪問看護もあるけれど、支援には限界がある。
どうしても「我慢してもらうしかない時間」ができてしまう。
その現実を受け入れることは、支える側としても本当にしんどい瞬間です。
けれど、そんな中で気づいたことがあります。
“支援”って、誰かが全部をやってあげることではなくて、できない日があることを前提に、一緒に考えることであると。

妻の調子が悪いときも、「無理に頑張れ」とは言いません。
そのかわり、「今日はしんどい日だね。どうすれば少し楽に過ごせる?」と声をかけます。
生活のリズムを整えたり、服薬を見守ったり、訪問看護と連携して少しずつ日常を積み重ねていく。
そんな日々の繰り返しが、少しずつ未来へつながっていきました。
体調が戻りつつある日、妻が「仕事してみようかな」と言いました。
うれしい反面、焦らずに進んでほしいという気持ちもありました。
「今日たまたま調子が良いだけかもしれない。悪い日でも生活できるくらい体調が安定してからにしよう」と伝えました。
その言葉に少し複雑な表情を浮かべながらも、「うん、わかった」と受け止めてくれたことを、今でもよく覚えています。
それから1年半。
妻は今、就職して4ヶ月。仕事のある日は疲れ切って寝てしまうこともありますが、それでも「自分の道」を歩けるようになりました。
本当に寄り添う支援とは

支援とは、ただ優しくすることではありません。
ときには厳しさが必要で、ときには静かに見守ることも必要です。
でも何より大切なのは、どんな状態の日も「あなたの隣にいるよ」という気持ちでいること。
寄り添うとは、背を向けないこと。
できなかった日も、うまくいかない日も、それを責めずに受け止めていけたら――
きっとその先に、また新しい一歩が見えてくるはずです。
そして今、私は就労移行支援の現場で、多くの利用者さんと関わっています。
妻との経験を通して学んだのは、「支援は“結果”よりも“過程”を見ることが大切」ということ。
できた、できなかったの一瞬ではなく、その背景にある努力や体調、環境の影響を丁寧に見つめること。
その上で「どうすれば次に繋げられるか」を一緒に考えていく。
誰かの人生に伴走するということは、急かすことでも甘やかすことでもありません。
支援者としても、家族としても、私はこれからも「背を向けずに寄り添う」姿勢を大切にしていきたいと思います。

発達障害に特化したエンカレッジ

発達障害のある人に特化したエンカレッジは、あなたの「働きたい!」をサポートします。
就労移行支援事業所は、大阪(本町、心斎橋、天満橋)・京都(京都駅、京都三条)・東京(早稲田駅前)・神奈川(横浜関内)の7拠点、自立訓練事業所は、encourage doors(北浜)で説明会の申込み・相談を受け付けておりますので、お気軽にご参加ください。